2025.06.04
ステマ規制摘発事例から学ぶインフルエンサー×PRでの注意点2025年版
販促
インフルエンサーマーケティングは近年急速に普及していますが、関連する法的リスクも増加しています。特に2023年10月に施行されたステマ規制により、インフルエンサーとのPR活動における注意点はより厳格になりました。
本記事では、実際に起きた違反摘発事例から、見落としがちな重要ポイントについて解説します。インフルエンサー施策を実施している企業のマーケ担当者はかならず知っておくべきポイントとなりますので、ぜひご一読ください。
目次
1. 国内で発生したステマ規制の摘発事例
2023年の10月に景表法の運用基準が見直され、いわゆるステマが行政処分の対象となるようになりました。これまでの間に国内でも数件摘発事例が挙がっていますので、その傾向と注意点について見ていきたいと思います。
なお、「そもそもステマ規制とは?」については過去の解説記事も参照ください。
1-1. 内科クリニック|クチコミ評価操作
2024年の6月に、ステマ規制が施行されてから摘発された第一号としてニュースでもよく取り上げられていたので、記憶にある方も多いと思います。
■概要都内にある内科クリニックで、インフルエンザのワクチン接種のために来院した患者に対して、Googleマップ上の当該クリニックのプロフィールに、★5または★4のレビュー投稿をすることを条件として、ワクチンの割引を適用した、というものです。
表示されたクチコミは「事業者による表示」に該当しますが、それ以外のユーザーに対してそれが明確にわかる表示になっていないことからステマ規制と判断されました。
こちらについてはインフルエンサーが関与した事例ではありませんが、ステマ規制の摘発事例第一号として取り上げました。
詳細については消費者庁の発表をご確認ください。
1-2. 大手プライベートジム運営会社 | SNS投稿流用時の表記不足
ステマ規制の事例2件目は、2024年8月に摘発されたプライベートジム業界最大手の企業です。
■概要
当該企業が展開するコンビニジムに関する宣伝において、2つの景品表示法違反で措置命令を受けました。
具体的には、
- ①「24時間全店舗追加料金なしで利用可能」といった表示をしてことが実態とは異なっていたことによる優良誤認表示と、
- ②SNS上のインフルエンサーによる投稿を自社サイトに転載する際に広告であることを明示せず、一般ユーザーの口コミであるかのように掲載していたことによるステルスマーケティング告示
この事例では、インフルエンサーの投稿を自社メディアで再利用する際も、広告であることを明示しなければステマ規制に抵触するため、コンテンツの二次利用時にも広告表示の義務があることを示す重要な教訓といえるでしょう。
上記の②の具体的な表示については、消費者庁の発表の中で、対象となったサイトが開示されていますのでこちらをご確認ください。
1-3. 大手製薬会社 | SNS投稿流用時の表記不足
事例の3件目は、2024年11月に摘発された大手製薬会社のサプリです。
■概要
当該企業の自社通販サイトにおいて、対象となったサプリのプロモーションとして、商品の無償提供と固定報酬を条件としてSNSへの投稿を依頼したインフルエンサーによる投稿を紹介する形で掲載しました。SNSの投稿内では#PRなどの記載がされていたものの、LP内ではこれらの投稿が広告であることを明示せず、消費者に誤認を与える形で使用していたため、ステマとして措置命令を受けました。
この事例からわかるのは、インフルエンサー投稿を引用掲載する場合、SNS側で広告と表示していたとしても、引用先でも広告であることを明示する必要があるという点です。
1-4. 大手製薬会社 | SNS投稿流用時の表記不足
ステマ摘発事例の4件目は、歯科クリニックのGoogleマップへの★5などのレビュー投稿の見返りとして施術料の値引き、もしくは金券をプレゼントしてレビュー操作を行ったもので1件目の内科クリニックとほとんど同じ内容でした。
続く2025年3月に摘発された5件目も3件目の内容とほぼ同じもので、企業こそ違えど同じような誤解をしてしまっている印象です。
対象となった目薬を、モニター募集サイト(商品の無償提供の代わりにSNSへの投稿をするインフルエンサーの公募サービス)で募集したインフルエンサーにSNS上で紹介させ、その投稿を抜粋し自社webサイトに掲載をする際、「私も使っています」という見出しで使用しましたが、一般消費者にそれらの投稿が広告であることを明示していなかったため、ステマとして措置命令を受けました。
こちらのケースでもSNS側では#PRの記載はつけていたということですが、引用先のLP側に記載が足りていませんでした。
上記の件の詳細は、消費者庁の発表をご確認ください。
2.直近の摘発事例からの注意点
インフルエンサーマーを起用した施策でステマとして摘発された事例をご紹介しましたが、各社共通してSNSでの投稿を二次利用した先での広告表示の不足という点が規制対象として摘発されています。
いずれも「お客様の声」のような形でLPにSNSの投稿を引用していましたが、昨今のUGC活用の観点では一般的な手法としてよく見られるものの、多くのマーケ担当者はこれがステマになり得るということにそもそも気付いていないのではないかと懸念されます。
UGC収集ツールなども様々ありますが、キャプション内でどのような形で広告と表示されているかはインフルエンサーによっても異なるため、ツール側で対応するのは難しい状況です。であれば、LP側で引用する際「インフルエンサーによるPR投稿が含まれます」という旨であったり、「無料モニターよる投稿です」などの記載をして、広告であることを明示する対応が現実的な対応策かと思います。
ただ、インフルエンサーによるコンテンツはいろいろな内容があり、必ずしも「お客様の声」のような形ではなく、例えばYouTuberが作ったコンテンツのような場合もあるため、その場合は上記の文言だと内容がずれてくるかと思います。
なんにせよ重要なことは、インフルエンサーによって投稿された内容はもちろん、二次利用した際に「その掲載の仕方で一般消費者に『広告であること』がわかりやすいか」という視点でよく確認をすることですので、ケースに応じてどのような記載が必要か、慎重に検討いただくことが欠かせません。
3.法令違反時の影響とペナルティ
インフルエンサーを起用する場合には、ステマ規制を含む景表法のほかに、薬機法などにも配慮が必要です。最終的には広告主である企業が責任を負うことになりますが、インフルエンサーマーケティングにおける法令違反は、企業に多方面から深刻な影響をもたらします。具体的な影響とペナルティを理解することで、コンプライアンスの重要性を再認識できるでしょう。
3-1. 行政処分と刑事罰のリスク
法令違反が確認された場合、企業には以下のような行政処分や刑事罰が課される可能性があります。
- ●措置命令:違反行為の中止、再発防止策の実施、一般消費者への周知
- ●企業名の公表:消費者庁ウェブサイト等での企業名と違反内容の公表
- ●刑事罰:薬機法違反の場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金
- ●課徴金:景表法違反で対象商品・サービスの売上の3%、薬機法違反で4.5%
景品表示法違反による措置命令は、消費者庁のウェブサイトで半永久的に公開され続け、企業の信用に長期的な影響を及ぼすと考えられます。 また、薬機法違反では個人(マーケティング担当者やインフルエンサー)も刑事責任を問われる可能性があります。
3-2. 企業の信用失墜と風評被害
法的な処分以上に企業にとって深刻なのが、信用失墜と風評被害です。具体的には以下のような影響が考えられます。
- ●ブランドイメージの毀損:消費者からの信頼喪失、ブランド価値の低下
- ●サジェスト汚染:企業名で検索すると「違反」「ステマ」などが表示
- ●SNS炎上:批判的投稿が拡散し、対応に膨大なリソースが必要
- ●メディア報道:否定的な企業イメージの拡散
一度失った消費者の信頼を取り戻すには、多大な時間とコストを要します。法令違反によって得られるかもしれない短期的な効果は、長期的な信頼喪失というリスクに見合わない可能性が高いでしょう。
3-3. 取引先への波及効果
法令違反は自社だけでなく、取引先にも影響を及ぼします。特に以下のような影響が考えられます。
■企業側への影響- ●取引先からの取引停止・契約解除
- ●新規取引先開拓の難航
- ●ECモールなどのプラットフォームからの出店停止
- ●他ブランドからの起用見送り
- ●所属事務所からの契約解除
- ●ファンからの信頼喪失
違反が発覚した場合、企業とインフルエンサーの両方が不利益を被る可能性があるため、双方の利益のためにもコンプライアンス遵守が重要となります。
3-4. 社内への影響
法令違反は組織内部にも深刻な影響をもたらします。
- ●社員の士気低下:企業への誇りや帰属意識の低下
- ●業務の中断:違反対応による通常業務への支障
- ●人事面での影響:担当者の処分、採用活動への悪影響
- ●内部統制の見直し:コンプライアンス体制の再構築コスト
- ●株価への影響:上場企業の場合、株価下落のリスク
法令違反による影響は、マーケティング部門だけでなく、企業全体に及ぶ可能性があるので、全社的なコンプライアンス意識の醸成が求められます。
まとめ
インフルエンサーマーケティングは効果的なプロモーション手法ですが、法的リスクも伴います。本記事で解説した違反事例や関連法令を参考に、適切なリスク管理体制を構築しましょう。
中でも重要なポイントは、広告であることの明示と根拠のない効果表現を回避することです。特に2023年10月に施行されたステマ規制により、広告であることの明示はより厳格に求められるようになりました。社内体制の整備、インフルエンサーとの適切な契約、継続的なモニタリングを通じて、法的リスクを最小化しながら効果的なインフルエンサーマーケティングの実現を目指すことが可能です。
透明性と誠実さを重視したインフルエンサーマーケティングは、短期的な効果だけでなく、消費者からの長期的な信頼獲得にもつながります。法令遵守と効果的なマーケティングの両立を目指し、安全かつ成功するインフルエンサープロモーションを展開しましょう。
株式会社千修では、お客様の多様化するニーズを汲み取り、“高いクオリティ“と”フレキシブルな対応“を両立させ、Digital&Physicalの枠を超えた様々なソリューションをワンストップでご提供します。
弊社はターゲットとなるユーザーに合わせて媒体の選定・コンテンツの制作・効果測定まで一貫して対応し、SNS運用・動画広告・インフルエンサーマーケティングなど、幅広い手法から最適な結果を追求します。
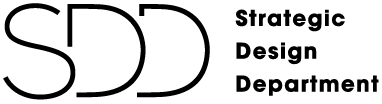













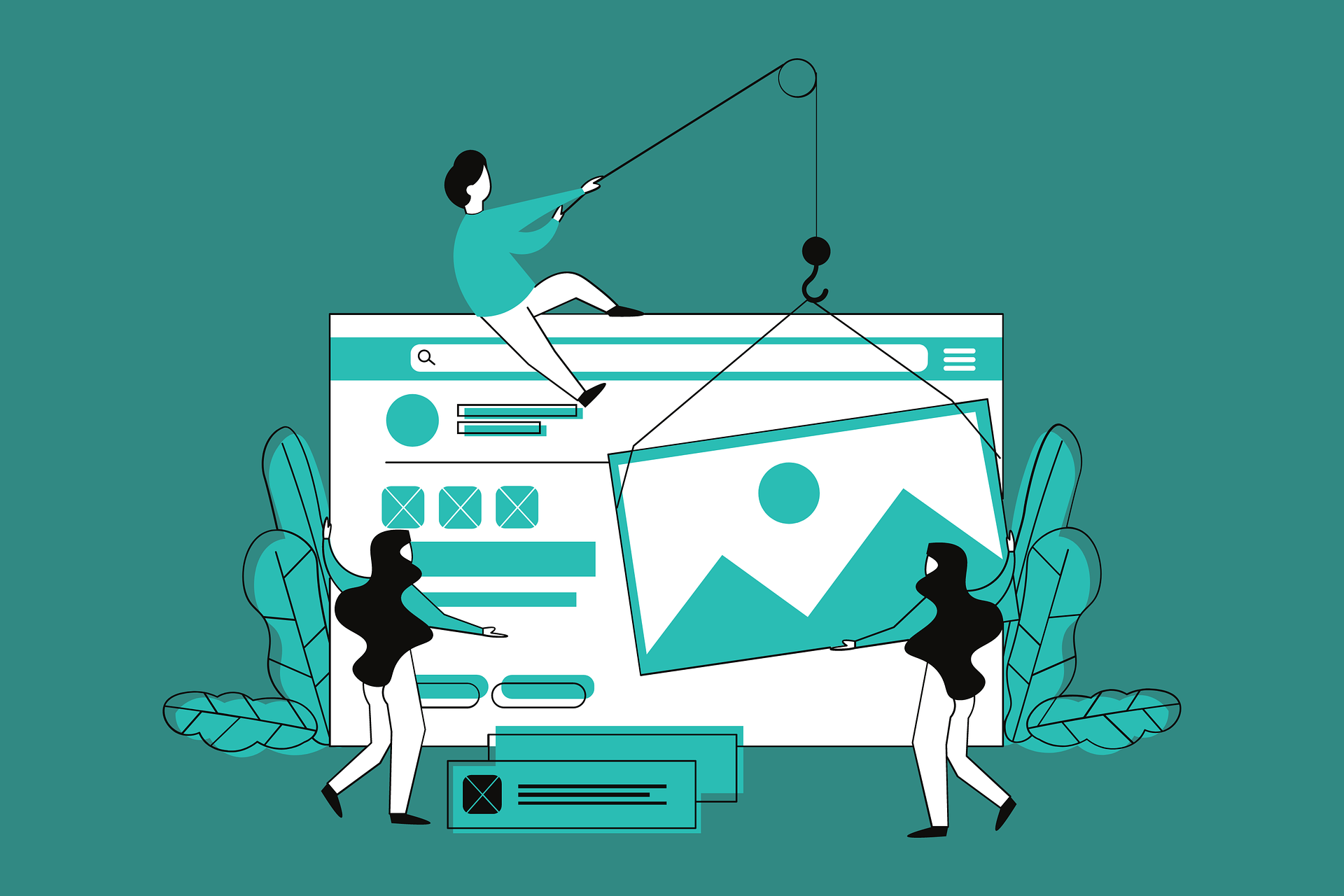
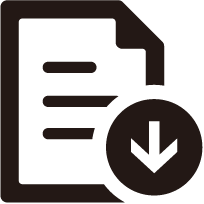 資料ダウンロード
資料ダウンロード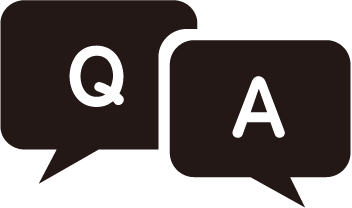 お問い合わせ
お問い合わせ